チラシ・フライヤー

チラシとは?特徴や種類、宣伝効果
チラシを見たことがないという人はいないのではないでしょうか?製品・商品や店舗の宣伝にもチラシは欠かせない存在です。
チラシは、宣伝したい内容が書かれた紙を「撒き散らす」ことから、「散らし=チラシ」と名付けられたと言われています。
語源のイメージ通り、大量に印刷し散らすように配布する折り込みチラシや店頭配布などでよく使用します。
今回はチラシの活用方法を3つご紹介します。
1.折り込みチラシ
チラシと聞くと、この新聞折り込みチラシが一番に頭に浮かぶのではないでしょうか。新聞に折り込まれて配達される「新聞折り込みチラシ」は、新聞を購読している層に直に届けることができます。
新聞折り込みのほか、カタログやパンフレットに挟んで使うこともできます。
形式としては両面もしくは片面の一枚刷りであるのが特徴です。
2.ポスティングチラシ
新聞配達などの配送を利用せず、各家庭のポストに直接チラシを投函する宣伝手法を「ポスティングチラシ」と言います。
新聞購読率が低下傾向にあるため、ターゲットの年代によってはポスティングが効果的です。
3.配布物としてのチラシ
街角やイベントなどで配布するチラシです。配布しやすいように折り込みやポスティングよりもコンパクトなサイズで制作することが多いです。
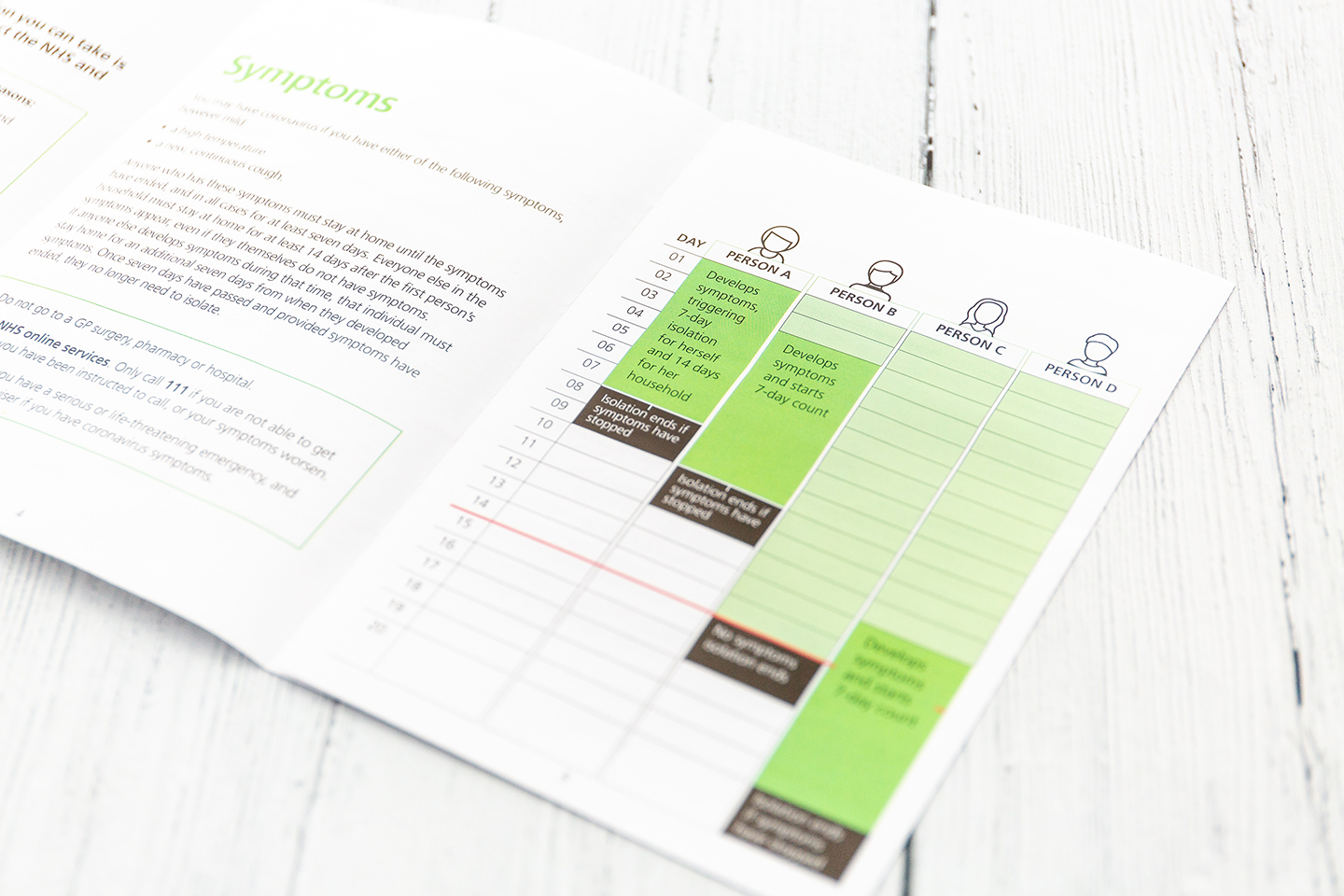
フライヤーとは?特徴や種類
フライヤーはよくチラシと混同されることが多いのですが、それもそのはず、「チラシ」は英語で「flyer」。元々は同じものであり厳密な違いはありません。
一般的にフライヤー制作というと、店頭や配布スペースなどでパッと目立つデザイン性の高い印刷物であることが多いです。
イベントや演劇の上映などの配布物をイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません。フライヤーはチラシに比べ、目を惹くような凝ったデザインや、おしゃれな雰囲気の印刷物をよく見かけます。
A6〜A4程度のコンパクトなサイズで、チラシに比べて紙厚なのも特徴です。

料金サンプル
下記金額はほんの一例で、その他のあらゆるタイプの制作・印刷に対応いたします。
営業担当者が内容をお聞きし、御見積させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
-
A4 チラシ
90,000円〜(内訳) 制作費:70,000円、印刷料:20,000円
・サイズ1:A4・2ページ
・サイズ2:(297㎜×210㎜)
・用紙:マットコート110kg ・加工:チラシ
・ページ:2P
・部数:1000






